【会員寄稿コラム】藤原秀郷流を訪ねて……《6》「晝日森天満宮」はどこ? ~田沼能忍地と藤姓足利氏
- 2025年7月18日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年7月20日
2025年7月18日
栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会
佐野支部 永島正光

昨年、足利家綱ゆかりの安楽寺(佐野市並木町)を訪ねた時のこと、ご住職から「天神様はもう行ったのかい?」、確かに天神様(朝日森天満宮)も家綱が勧請した神社、秀郷流佐野氏の氏神でもあり、元々は唐沢山の西側「天神沢」にあったので天神様と呼ばれている。「まだなんですよ」、「実はね、その昔この佐野庄には三天神と言われた天満宮があり、朝日森、晝(昼)日森、夕日森と呼ばれ、他の二つも何処かにあるそうだよ」、「そうなんですか、ありがとうございます、探してみます」 ※(晝=昼)
なるほど、ちょっと気になる。早速ネットで検索してみると「夕日森天満宮」がヒット、多田町の賀茂別雷神社にあると言うので行ってみる。
拝殿の右側に集合殿という建物があり、いくつかの神社が祀られていて、真ん中に大きく立派な社が「夕日森天満宮」でした。造りや彫刻も素晴らしいので近年の再建のようです。ただ、ここに合祀されていると言うことは、摂社、末社で元々は近くの別のところにあったのでは。
一つ残念なのは、名前です。夕日森天満宮と書いた安っぽい赤い紙が無造作に右側の柱の貼ってある、しかも斜めに。なんか怪しいし、大丈夫?と、せめて板に毛筆で書き社殿にとの思いが。
ここの毛利宮司とは面識があり、ご挨拶、雑談の後「昼日森天満宮もあるそうですが、毛利さんはご存知ですか?」、「はい、この辺りの寺院の入口付近にあると言う話は聞いたことがありますが、行ったことはないんですよ」、「そうですか、ありがとうございました」
近くの寺院?浮かんだのは西林寺(田沼家菩提寺)、本光寺(佐野家菩提寺)、密蔵院、とにかく行ってみよう。お急ぎ一時間半……、見つからない、残念、残念。
半年後、別の調べ物で佐野図書館へ。大正四年に書かれた「安蘇郡内誌」、一瓶塚稲荷神社の項目に「晝日森天満宮は一瓶塚稲荷神社の境内にあり」の記述を発見、俄然やる気再燃、早速行ってみる。
社殿右奥に合祀されている摂末社が9社、その中に「天満宮」が確かにあるのだが、「晝日森」の文字はなく、なにより新しい。大正四年以前のものとは到底思えない、再建したと思えなくもないが、いまいちスッキリしない。
再度ネット検索、「田沼町史」に
なにやら記述があると言うのでまた図書館へ。「旧田沼町の電話局入口西側にあったが、昭和41年(1966)、北方にある愛宕山麓の運動公園造成工事の際移転された」とあり、これは直ちに行かなくてはと。
旧田沼町電話局の周りぐるぐる廻り探すがそれらしき形跡は見当たらず運動公園へ。
公園入口右側に愛宕神社があり、石碑が二つ見える。「移改築記念碑、昭和42年」「蛙のなかぬ池の歌碑」移転ということは、公園ができる前は別な所にあったということになる、時期的には合っているが、「天満宮」ではない。そして公園北の愛宕山頂上にもう一つ愛宕神社があるので、「本宮」と「奥の院」と言うことなのだろうか。
いよいよ愛宕山頂の奥の院へ…一の鳥居が切ない(社額の文字が消えてる)参道の石段を登り始めるが、一直線なのだが藪も凄いし先が全く見えない。猛暑日のこの日、水分補給し休み休み登ること320段!(帰りに数えた)やっと社殿が見えてきた。近年再建されたようで綺麗、遠望も素晴らしい。それよりも気になったのがこの「庚申塔」数も凄いが見たこともない巨大な「千庚申塔」、信仰の凄さを改めて見せつけられたような気がしました。
ところで例の「晝日森天満宮」は見つかりません、頂上にあったのは「妙義神社」の石祠だけ、まてよ、たしか一の鳥居の右上に鳥居がもう一つあった、戻るぞ。
あった!石も含めて摂末社が七つ、長屋風の二番目と四番目が天満宮、晝日森の文字がないのは残念。少し不安はありますがどちらかが「晝日森天満宮」だろうと思うことにします。
今回の「晝日森天満宮」を探せ!で舞台となったのは旧田沼町の田沼町、多田町、栃本町、山越町地区、特に愛宕山南方は「能忍地」と呼ばれ肥沃な土地で古くから沢山の人々が暮らしてきたようです。
調べ始めると秀郷流の足利さんがたくさん登場しました。藤姓足利氏は渕名大夫兼行の子、成行(しげゆき)が1052年に足利両崖山に城を築き初代足利氏となり、約120年この地を領しました。
そして、二代目成綱(なりつな)は早世、三代目を継いだ家綱は幼く足利行国(初代成行の弟行房の子)が後見人となり本家筋を盛り立てます。家綱、四代目俊綱と続き全盛期となりますが、1110年頃に上司的立場だった源義国(八幡太郎義家の三男)は本貫新田庄よりじわりじわりと藤姓足利領の利権を削って行き次第に敵対していきます。
1150年頃には、家綱は足利を去りこの能忍地に居を構え余生を過ごしたようです(墓は愛宕山奥の明菊山山麓、また戒名に能仁寺…ともあり)。また、俊綱もここに何年か居住し晩年赤見に移ったと言われている。

そして、足利成俊(しげとし、俊綱の弟)は五社稲荷神社(富士町、秀郷創建)を田沼に勧請移転、一瓶塚稲荷神社を創建し鎮守とする。また能忍池(能忍地にあった湿地帯)の神様、白龍神(民話、伝承から)を祀って愛宕神社を創建します。しかし、本来なら佐野庄司として佐野氏初代となるはずでしたが、残念ながら後継のないまま早世してしまいます(娘がいて佐野基綱に嫁いだとか)。
秀郷流で足利を名乗った最後の武士、足利有綱の鞍掛神社もすぐに近くにあるし、今回の三天神もみんなこの辺りにあった。

平安末期一族にとってこの地、田沼能忍地が安住の地だったのではと。
1180年の源平合戦の初戦で藤姓足利氏一族は上州秀郷流も引き入れ平家に与し、宗家忠綱を大将とし大活躍、平家勝利に貢献しましたが、恩賞問題で一族は分裂し宗家は孤立してしまいます。1182年の野木野宮合戦では不本意ながら、反頼朝となり運なく五代目忠綱で滅んだ藤姓足利氏ですが、敵対となってしまった有綱の長男基綱は佐野氏を名乗り以後400年余りこの地を守り続けます。
忠綱が平家から賜った「揚羽蝶」の家紋は佐野家に引き継がれて現在でも寺社仏閣などで見かけます、思いは受け継がれているのだと。
成行を祀った藤宮神社、成綱、家綱の相撲節会(宮中相撲大会)、「一国之両虎」と呼ばれた俊綱、瀬田の橋合戦の忠綱…足利の姓を名乗っていても足利市には藤姓足利氏の面影を感じるものはほとんどありません、ここも「歴史は勝者が創る?」なんでしょうか。
しかし、ここにはあります。藤原秀郷だけでなく、その子孫の彼らが残した寺社仏閣、伝承、民話、慣習など、佐野氏子孫などの郷土の有志によって守られ今に引き継がれて来ているのです。
参考資料
田沼町史 佐野市史 安蘇郡内誌 戦国唐沢山城 出居博
佐野の民話 佐野ロータリークラブ





















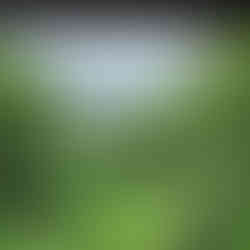















コメント