

【会員寄稿コラム】ここから古への想い《1》
2026年1月25日 栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会 佐野支部 永島正光 多気城碑 「多気山城から見る名門宇都宮氏の終焉」 「これで北条が進軍して来ても、いち早く備えができよう」 1585年(天正13)小山秀綱を蹴散らし、怒涛の北征を続ける小田原北条氏。ビビる宇都宮国綱は本城を宇都宮からここ多気山に移します。確か前方は見通しはきくが……西の鹿沼方面はみえない? 鳥瞰図(余呉さんのHPより) 道しるべ(多気山頂) 1588年(天正16)北条氏に降った皆川氏に西方城を、奪われた国綱、佐竹の援軍を得て皆川氏の出城諏訪山城に襲いかかる。 圧倒的な兵力で皆川勢を攻め続け諏訪山城、真名子城、富張城(神楽岡)、深沢城(布袋が丘)へと押しまくる。吹上城を落とし残るは皆川本城、しかし、皆川軍の後詰め壬生義雄に手薄の多気山城を狙われ、急遽無念の退却… 鹿沼の城郭 1590年(天正18)豊臣秀吉の小田原征伐で宇都宮18万石を安堵された国綱だったが、跡継ぎ(男子)がいない…、秀吉から子飼い重臣、浅野長政(秀吉の正妻、ねねの親族)の二男長重を養子にと勧められる。国綱


『おじ散歩』レポート
2026年2月7日 栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会 専務理事 岡田康男 栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会の宮本代表、水野顧問と一緒に、おじさん3人で『おじ散歩』と洒落てきました。 3月28日に開催予定の秀郷ベント「皆川氏巡り(仮)」の下見を兼ねて、栃木・皆川城内地区へ。皆川城址と皆川の菩提寺金剛寺へ。天候がイマイチでしたが、まずは久しぶりの皆川城址。 以前よりもキレイに整備され、全容もはっきり見え、なかなかかっこいいですね。そうです!カッコいい山城なんです! 今も皆川地区を見下ろす皆川城全景 金剛寺前から 皆川城址公園案内図 往時の城の面影を感じさせてくれる形状が、しっかり残っています。 城址全体に桜の木が揃っているので、イベント開催の3月末頃は桜が見頃になるようです。楽しみ!! 桜が楽しみな桜平 2月の今は、蝋梅と紅梅が見頃。 蝋梅が見頃でした 蝋梅と紅梅の共演 全体のよく整備され歩きやすくなっていますが、さすがに本丸(頂上)近くは急坂です。 本丸へもう一息、登りやすく整備されているのでありがたい 本丸(頂上)には見晴し台が整備され、


【水野先生コラム】『おじ散歩』レポート
2026年2月7日 栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会 顧問 水野拓昌 2月7日の土曜日、栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会の宮本さん、岡田さんとともに栃木市の皆川城跡、金剛寺に行ってきましたよ。3月28日予定の交流会の下見です。 栃木市中心部の少し西側にある皆川城跡は、藤原秀郷の子孫・皆川氏の居城です。戦国時代の山城の跡で、標高147メートルで、それほど高くなくて、下から山頂の展望台が見えるので、すぐ登れそうな感じもします。法螺貝城とも呼ばれたように、螺旋状でくるくると登っていくので、急斜面はあまりありません。その分、距離はあって、かなり登ってきたはずなのに、まだ着かないのかなぁ、と思いもします。 実は過去にも数回登ったことがありますが、年齢を重ね、勾配が急だと思う箇所がありますね。今は梅や蠟梅が少し咲いている程度ですが、3月末だと、桜がかなり咲いているはずです。ふもとは公民館があり、駐車場があり、広場があります。山頂までだいたい20分。途中休憩を取りながらゆっくり登って30~40分程度だと思いますよ。山頂からの見晴らしは素晴らしいですよ。


【会員寄稿コラム】藤原秀郷流を訪ねて《10》「古河城のその昔~下河辺行平と頼政神社」
2026年1月12日 栃木の武将藤原秀郷をヒーローにする会 佐野支部 永島正光 古河市渡良瀬川にかかる三国橋、南東の土手のにある「古河城跡」の石碑。行ってみると見渡す限りの土手と広い河川敷、遺構なんて見当たらない。 江戸時代の縄張り図を見ると、渡良瀬川東の沼地に突き出した舌状大地を利用した縦長の平城です。本丸には天守閣代わりの三重櫓もありましたが、明治時代に渡良瀬川河川工事でほぼ壊滅、後付けの石碑だけが……ところで中世以前の古河城の創健者は?下河辺行平とありました。 それと気になったのは、縄張り図にある頼政曲輪と頼政神社、そして左上の神社の現在地。頼政ってあの源頼政(源三位)、平安末期1180年(治承4)平家打倒の挙兵に以仁王と共に先陣をきり宇治川で平家軍と激突しましたが大軍の前に無念の敗戦、平等院で自刃してしまった摂津源氏の棟梁です。 下河辺行平と源頼政の関係は……。 下河辺氏は藤原秀郷流小山氏族、平安末期下河辺地区(下総領内、現在の茨城県古河市、五霞町、埼玉県加須市あたり)に土着した一族。行平の父行義は、当時下総国守をしていた源仲政
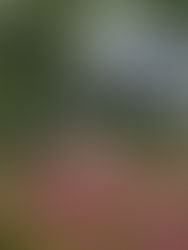

【会員寄稿コラム】藤原秀郷の系譜をたどって―― 初夏の近江・日野町を歩く
2026年1月30日 栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会 会員 寺内 明子 6月、藤原秀郷をヒーローにする会の活動も兼ねて、滋賀県蒲生郡日野町を訪れてきました。日野町は、藤原秀郷公の子孫である、のちの会津藩92万石の領主、蒲生氏郷公の生誕地であり、宇都宮とも縁の深い「近江日野商人」の町です。 これまで資料や系譜として知ってきた場所を、今回は実際に歩き空気を感じながら巡ることができました。 凛とした姿の中に、どこか落ち着きと品を感じる街 街に入ってまず目に入った蒲生氏郷公の銅像。藤原秀郷の系譜に連なる人物として、これまで何度も名前を目にしてきましたが、実際にその地に立ち像を前にすると、歴史が一気に身近に感じられました。 この街で育まれた時間を、静かに見守っているような氏郷像 日野という土地そのものが、氏郷公の人柄や価値観を形づくってきたのだと、町の空気から自然と伝わってきます。 かつての歴史を感じながら、ゆっくり深呼吸したくなる場所です 日野城跡は、緑に包まれたとても静かな場所でした。 ここが政と武の拠点であったとは思えないほど、今は穏やか

