【会員寄稿コラム】藤原秀郷流を訪ねて《8》 佐野四天王「山上道及」を追いかけて
- 2025年9月8日
- 読了時間: 5分
2025年9月8日
栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会
佐野支部 永島正光

大河ドラマ「べらぼう」の影響は凄い。田沼意次、意知父子や佐野政言のおかげで、彼等の先祖の発祥の地とされる佐野庄(佐野市)にはこの夏以降来訪者が増えたとか、嬉しい限りです。特に、関係のある寺社仏閣や施設には自称「歴史研究家」とおぼしき年配者が訪れ、思い思いの質問や問い合わせなどをして来るようですが、嬉しくもありそれ以上に、「大変でもあり」が本音のようです。対応された方々は全員が歴史専門家ではありません、あまりのマニアックさに「私にはわかりかねます、申し訳ございません。」「えっ、知らないの?」。こんなやり取りをする来訪者を対応する人達は「べらぼうオジサン」と呼んで警戒?しているとか。
そんな中に「佐野四天王って知ってる?」今回はこれを取り上げてみました。
四天王と言えば有名なのは徳川四天王、武田四天王など、大河ドラマ「光る君へ」では道長四天王もありました。しかし、佐野四天王となると「そんなのあったの、だれ…?知らな~い」こんな感じですね。
戦国時代佐野家に仕えた武勇に優れ知略に富んだ四人、大貫越中守定行(武重,政宗とも)、山上道及(道牛,氏秀、照久とも)、竹沢(武沢)山城守定冬、津布久弾正です。その中でなかなか個性的で知る人ぞ知る「山上道及」を取り上げました。
⑴どこのどんな人
山上氏は勿論藤原秀郷流です。始祖は藤姓足利家綱の五男高綱、平安末期に上野の国、赤城山麓に移住し山上姓を名乗り、1183年(寿永2)頃山上城を築き居城とする(新里村誌)。1555年〈弘治元年〉山上城は北条氏康に攻められ落城、城主氏秀(道及)は足利長尾当長を頼り落ち延びるがここも北条氏康に降り今度は佐野泰綱のもとで家臣となる(新田老談記より)。
*新田老談記、唐沢山老談記は江戸時代初期に書かれた軍記物と呼ばれる物語で創作色が強く信憑性には疑問が残りますので諸説、伝承の取り扱いですね。山上氏系図(田原族譜)には初代高綱から五代秀光までで氏秀(道及)への系譜は不明です。
⑵何をした人
①佐野泰綱(13代)からの絶大なる信頼。1545年(天文15年)の泰綱掟書き(遺言)の一文「巨細は山上美濃守に申し含め候」。但し年代の整合性が取れないので道及の父親説もあり。
②1568年(永禄11年)佐野昌綱(15代)に重臣津布久昌成を弔う「大庵寺」創建を提案実行(二人とも浄土宗)
③1571年(元亀2年)故津布久昌成の三回忌法要時の道及、参加者と念仏の辺数(回数?)
④1579年(天正7年)京都にて絵師松栄(狩野元信の三男)に主君佐野昌綱の肖像画を描かせ大庵寺に奉納
⑤1581年(天正9年)免鳥城の戦い(対足利長尾顕長)足利長尾勢が免鳥城を攻撃の報に道及等60騎救援に駆けつけるも城は落城、城主高瀬紀伊守は討ち死に。戦半ば敵大将との一騎打ち見事勝利した道及の形相に足利勢は「山上道及は鬼神か!」と尻込みしたとか。(唐沢山老談記)
⑥1590年(天正18年)下野絵図 天徳寺宝衍と共に上方で豊臣秀吉仕えていた道及、秀吉が小田原征伐に下野絵図を所望。天徳寺宝衍が道及他四名に作成を指示、完成後加藤清正に呈した。
⑶天徳寺宝衍と共に
山上道及は1581年の免鳥城の戦い後、武者修行と称して佐野家を出奔てしまいます。1585年(天正13年)の須花の戦いでの佐野宗綱(16代)の討ち死にを知ったのは武田領内にいた時のようです。直ちに秀吉のもとにいた天徳寺宝衍と合流、秀吉に面会し宝衍と共に秀吉の小田原征伐、関東案内役を担うことになります。下野絵図の作成、また秀吉が小田原征伐の際関東諸将に出した「惣無事令」の伝達使者の重責も果たしています。
かくして二人は秀吉軍の北国軍に属し先方を担い1590年(天正18年)7月、複雑な思いを抱えながら唐沢山城を5年ぶりに奪還するのです。
この戦いで城を守っていた北条方の城代は佐野四天王の一人、大貫越中守定行「不本意ながら訳あって敵味方となりましたが、今の主君は氏忠様、許可なく降伏したとあっては殿に顔向けができません。忠義を全うさせて頂きます」。天徳寺宝衍は「切腹させるほどのことはなかったものを、我らが下がって様子を見届け、少々のことは罪を許しておくべきだった」(唐沢山老談記)
道及は翌年重臣として、領民に「不作地をひらくべきの定」を出すとの記録がありますが、それ以降の足跡の資料が殆ど残っていません、この頃は既にかなりの高齢と思われ、亡くなったとの説もありますが…。
⑷山上道及の夢物語
1598年(慶長3年)上杉景勝会津移封の際「新規召し抱え牢人に道及の名あり」こんな記述があるとか。浪人ではなく牢人(囚われ人?)何か意味ありそうです。
山上道及の武者修行は情報収集、秀吉の世を予想していたのかも知れません。宝衍と共に秀郷流佐野氏を復活させた道及は秀吉亡き後を考えていた(実際は亡くなっていたかも)。
西軍石田三成に賭け、最後は戦場でとの思いがあったのでは。
1600年(慶長5年)慶長出羽合戦(北の関ヶ原)直江兼続軍(上杉景勝)対最上、伊達連合軍。直江軍優勢のさなか、関ヶ原での西軍石田三成の敗退の報。やむなく退却する直江軍、殿は直江兼続本隊、前田慶次、そして山上道及。
人気漫画「花の慶次」原哲夫様、粋な演出をしてくれました。 【花の慶次~戦国後日譚~】
「山上道及のその後。」 ↓ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3451742124953473&id=291963580931359&set=a.344555209005529
参考資料
「郷土史論考」高崎 寿
「開け行く安蘇」佐野市教育会
「田原族譜」山士家左俜
「田沼町史第3巻、6巻」
「佐野氏と唐沢山城」「佐野の城館跡」佐野郷土博物館
「新田老談記」
「唐沢山老談記」 他











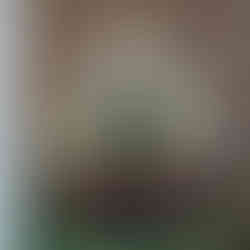











コメント