【資料公開】第15回 藤原秀郷 交流会『歴史カフェ』-2025年7月19配付資料
- 2025年8月8日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年8月12日
お米を知れば日本が見えてくる!
「お米から理解する日本の歴史と基礎知識」
年収・物価・各種単位・度量衡

日本人にとって、なくてはならない大切な「お米」。
江戸時代までは、将軍でも、大名でも、庶民に至るまで、その暮らしの基本となる単位「度量衡」のベースになっているのは「米」でした。そんな重要な「米」ですが、江戸時代には一体どのくらい採れたのでしょうか?大名の格や藩の規模を表す「石」という単位は、どのくらいの規模を示すのか、知っていますか?意外に知らない歴史の「単位」…その原理や数値を知ると、その時代の暮らしや成り立ちが、驚くほどはっきりと見えてきます。知っているようで意外に知らない暮らしの単位とその考え方、そして基礎知識を、わかりやすく考えてみましょう。
■ 目次
■ 江戸の大名の経済力は?
※江戸時代・前期・中期・後期により変化する。 下記:※註1参照
●日本の総石高 約3000万石(幕府25%、大名75%)
幕府領・・約700万石(旗本領地を含)
大名領・・約2,300万石
●武士のランク
大名 1万石以上 10億円以上 260〜300人
旗本 100石以上 1,000万円以上 5,000〜5,200人
御家人 100石以下 1,000万円以下 17,000〜18,000人
1万石以上5万石未満=約65% 5万石以上=35%
●武士の区分け
・親藩(しんぱん)…家康の直系を中心とした将軍家に近い親類の大名家。
・譜代(ふだい) …徳川の家来。譜代=「代々(つかえてきた)」という意味。
有力な旗本たちは1万石以上の大名となり地方の要所を治める。
徳川四天王(酒井、本多、榊原、井伊)や、大久保、鳥居、土井、
奥平、久世、小笠原などの有力大名とそれらの分家。
・外様(とざま) …よそ者(客人)
関ヶ原の合戦以降に徳川家に臣従した「上方衆」と呼ばれる旧織田
系・豊臣系の大名や地方の名門家、旧家の大名。
※内訳(1664年(寛文4年)時点)
・親藩(御三家を含む) 12人
・譜代 113人
・外様 100人計 225人
○御三家(ごさんけ)…尾張 紀伊 水戸
○御三卿(ごさんきょう)…田安 一橋 清水

■ 江戸時代の武士の給料は?
●武士の俸禄は、大きく分けて5種類
・知行取り(石)・・・主に旗本で200石以上
(例1)200石×四公六民0.4=80石
合計約840万円(※1:米価3,500円/5kgで換算)
(例2)200石10人扶持(男5・女5)
200石×四公六民0.4=80石
男扶持:1日5合×354日×5人=約9,000合=9石
女扶持:1日3合×354日×5人=約5,400合=5.4石
合計80石+14.4石=94.4石
合計約990万円(※1:米価3,500円/5kgで換算)
(例3)50俵3人扶持
50俵=20石=210万円
扶持:1日5合×354日×3人=約5400合=5.4石=567,000円
(※1:米価3,500円/5kgで換算)
合計2,667,000円
・蔵米取り(俵)・・・主に御家人
(例)200俵=80石=840,000円
・現金支給・・下男・牢守など下働き、雑用
・部屋住・・・嫡男であるが家督を継いでいない者
役職についていれば俸禄がある
・隠居・・・現役時の役職による
●江戸の給料をわかりやすく!(※1:米価3,500円/5kgで換算)t
将 軍 500万石=500万両=5250億円
大 名 例:40万石〜=40万両〜=420億円〜
旗 本 40〜4,000石=42万〜4,200万円
御家人 40石以下=42万円以下
町奉行(南北) 1050石=1億1,000万円
町奉行 420石=4,400万円
与力25人 60〜80石 630〜840万円
同心120人 30俵十両 230万円
岡っ引き 1分=26,000円
商人・棒手振り(売り歩き:天秤にて街中で移動販売)
日当500文 約13,000円
歌舞伎役者 100〜500両 1,050万円〜5,250万円

■ 江戸時代の物価は?
(江戸時代中後期の説 ※註2)
●価格例
上級花魁:1両1分=225,000円
部屋持ち花魁:1分=25,000円
歌舞伎 桟敷席一席 銀164匁(0.164両)=49,200円
旅籠(食事付き):60〜200文=3,000〜10,000円
米1kg :30文=1,500円
醤油1升:銀0.7匁=500円
砂糖1升:銀4匁=3,000円
卵1個:7〜20匁=60〜200円
大根1本:7匁=60円
蕎麦1杯:16文=800円
寿司握り1貫:8文=400円
茶めし1膳:50文=2,500円
うな丼1杯:200文=10,000円
長屋の家賃(10畳):90文=4,500円
銭湯(大人):6文=300円
長命寺の桜餅1個:4文=200円 (山本や 現在250円)
※註3:2023年米収穫高 680万トン=4,500万石
1石=150kg
新潟県 450万石
■ 江戸時代の貨幣単位は?
※江戸時代の貨幣単位は複雑でわかりにくい。
1両=4分(歩)
1分=4朱(しゅ)
大判=10両
小判=1両
1両=銀1貫目=1,000匁
=銭4貫文=4,000文(米価基準による)
※価値の変遷
江戸初期(1609〜)1両=銀50匁=銭4,000文・・・100,000円
江戸中期(1700〜)1両=銀60匁=銭4,000文・・・200,000円
江戸後期(1840〜)1両=銀60匁=銭6,500文・・・300,000円
江戸幕末(1868頃)1両=銀60匁=銭8,000文
■ 秀郷の時代(平安時代)の貴族の給料は?
藤原道長はいくらもらっていた?

■ 日本の基本情報

●暦
29.5日/1月 354日/1年
調整で閏月・閏年あり
●日本総人口
江戸時代1600年頃・・・1,200万人
江戸末期1838年頃・・・2,800〜3,000万人
江戸100万人 ロンドン70万人 パリ50万人
●日本の総石高
約3,000万石(幕府25%、大名75%)
幕府領・・・約700万石(旗本領地を含)
大名領・・・約2,300万石
●江戸時代の耕作地
1600年頃 164万町 1720年頃 300万町 (1町3,000坪100アール 約100×100m)
●幕府の財政収入
400万両 家臣の領地も含めると800万
吉宗時代でも463万両 現代の価値で1兆3890億円
(ちなみに)加賀百万石・・・102万5,000石(3,075億円)
●価値基準
(※註2:大工見習いの日当15,000円で換算すると)
1石 1両 60匁 4,000文 300,000円
1石 =150kg=約100,000 (※註1参照)
基準=米ベース
(ちなみに江戸後期1両で大工約20人を雇えたという※註5参照)
●食料基準
1日3食
1食・1合×1日・3食×354日=1石=1,000合
■ 江戸時代の度量衡(換算表)

下記ページより、今回公開した資料をはじめ、過去のイベントで配布した資料のアーカイブ(ファイル形式:PDF)をご覧いただけます。ぜひご活用ください!
※ アップしている資料は 無断で転載、配布、加工などを行うことを禁止しております。個人利用の範囲でご覧ください。

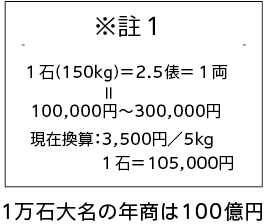
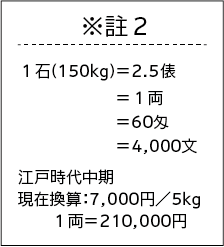
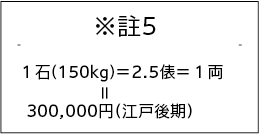


コメント